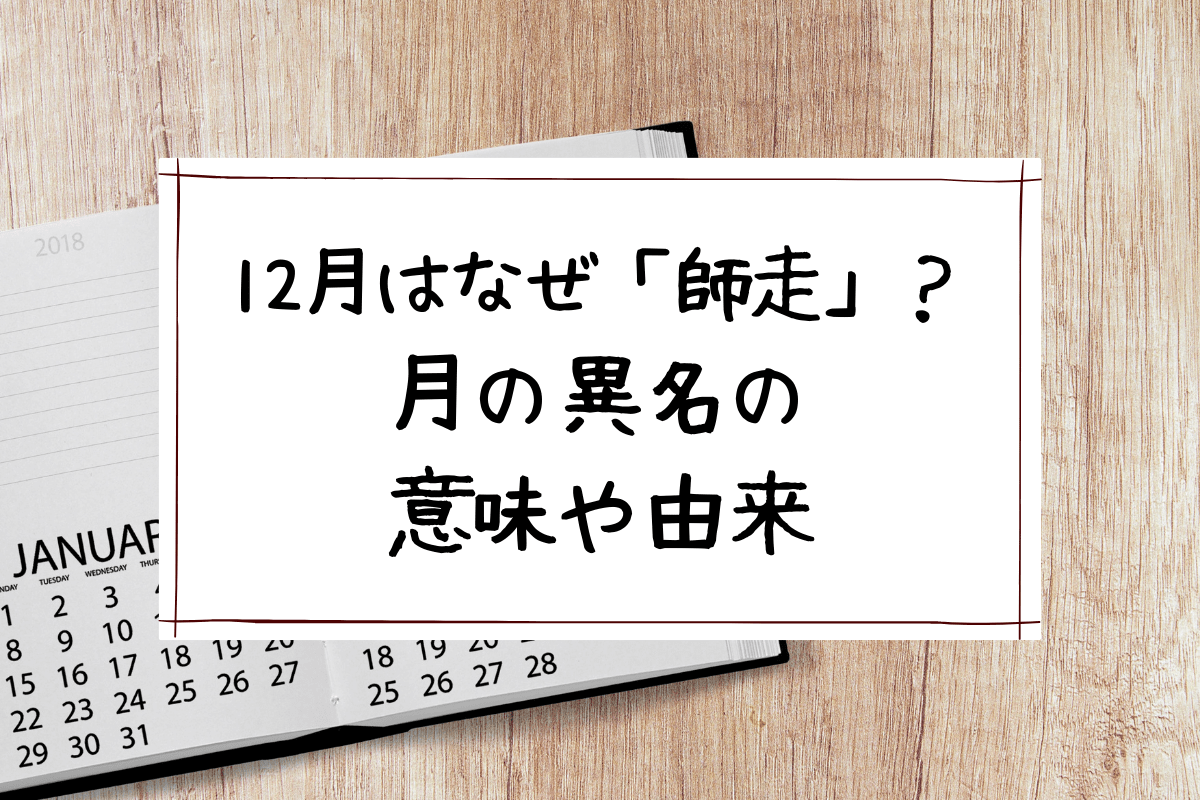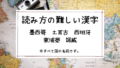12月は、別名「師走」とも呼ばれます。ほかにも、1月は「睦月」、2月は「如月」…といったように、月にはそれぞれ「月の異名」が付けられています。
どうしてそんな名前になったのか、その由来を解説しつつ、異名の覚え方についても紹介していきます。
スポンサードサーチ
月の異名の由来
月の異名は万葉集や日本書紀にはすでに登場しているほど、古い時代から使われています。
|
1月 |
睦月(むつき) |
| 2月 |
如月(きさらぎ) |
|
3月 |
弥生(やよい) |
|
4月 |
卯月(うづき) |
| 5月 |
皐月(さつき) |
|
6月 |
水無月(みなづき) |
| 7月 |
文月(ふみづき) |
|
8月 |
葉月(はづき) |
| 9月 |
長月(ながつき) |
|
10月 |
神無月(かんなづき) |
| 11月 |
霜月(しもつき) |
|
12月 |
師走(しわす) |
1月の異名:睦月(むつき)
1月が「睦月(むつき)」と呼ばれるのには、2つの説があります。一つ目は、お正月には家族や親せきなどがたくさん集まり「睦まじく過ごす」ということから「睦月」となったという説。
そしてもう一つは、1年の始まりであり元になる月なので「もとつき→むつき」と転じたのではないか、という説。どちらの由来にしても、1月といえばお正月があり、1年の始まりである、ということが元となっています。
2月の異名:如月(きさらぎ)
2月が「如月(きさらぎ)」と呼ばれるのには諸説ありますが、最も有力な説は、「着更着」から来ているというもの。2月は寒さが厳しい月なので、着物を更に(重ねて)着る=着更着となったと言われています。
その他には「生更木(木が生え始める)」などが元となったのではないか、という説も。「如月」という漢字が当てられているのは、中国で2月を表す言葉から来ています。
3月の異名:弥生(やよい)
3月が「弥生(やよい)」と呼ばれるようになった理由は、3月が春の訪れを感じさせる季節だからです。「弥=ますます」「生=(草木が)生い茂る」ということから、春の芽吹きの季節=弥生と呼ばれるようになりました。
4月の異名:卯月(うづき)
4月が「卯月(うづき)」と呼ばれるようになったのは、卯の花が咲く季節だから。他の月に比べると安直な由来だなと感じるかもしれませんが、卯の花のほんわかとしたイメージは4月にピッタリですよね。
5月の異名:皐月(さつき)
5月は苗を植え始める季節。そこから「早苗月(さなえづき)」→「皐月(さつき)」と変化していったと言われています。
また、「さ=耕作」を意味することから、さつきと呼ばれるようになったという説も。
6月の異名:水無月(みなづき)
6月が「水無月(みなづき)」と呼ばれる理由には、2つの説があります。まず梅雨明けで水(雨)がもう降らない、または田んぼに水を引いているので他の場所に水が無いので「水が無い月」、という説です。
もう一つは、逆に梅雨明けで田んぼなどに水が多くある=水の月(この場合「無」は「の」という意味で使われている)という説。
7月の異名:文月(ふみづき)
7月と言えば七夕がありますが、このとき短冊に歌や字を書くことから「文月(ふみづき)」と呼ばれるようになったと言われています。
その他にも諸説あり、稲穂が膨らみ始める「含み月(ふくみづき)」が転じて文月、稲穂の膨らみが見える「穂見月(ほみづき)」が転じて文月になったという説などがあります。
8月の異名:葉月(はづき)
現在の8月は夏真っ盛りという感じですが、旧暦の8月は現在で言えば9月ごろ。植物の葉が落ち始める月なので、「葉落ち月」を略して「葉月(はづき)」となったと言われています。
他にも稲穂がパンパンに張ってくるので「張り月」が転じて葉月となったという説も。
9月の異名:長月(ながつき)
9月が「長月(ながつき)」と呼ばれる理由は、「秋の夜長」から来ています。秋の夜長=夜長月=略して長月と呼ばれるようになった、という説が一般的。
しかしその他にも、雨が多い季節だから「長雨月=略して長月」という説や、「稲刈月(いなかりづき)」が転じて長月となったという説などがあります。
10月の異名:神無月(かんなづき)
1年の暦の内、最も多くの説があるのが「神無月(かんなづき)」。一般的には、10月には島根県出雲大社に全国の神様が集まる「神在祭」が行われることから、他の地域には神様がいなくなる=神無月と呼ばれるようになったというのが、広く知られています。
また、神様を祭る月なので「神の月(この場合も「無」は「の」の意味)」という説や、「雷が鳴らない月(雷無月)が転じて神無月」になったという説など、様々です。
11月の異名:霜月(しもつき)
11月は霜が降り始める季節なので、「霜月(しもつき)」と呼ばれるようになったといわれています。
12月の異名:師走(しわす)
12月は年末年始に向けて、もっとも忙しくなる月。「師」というのは、一般的には僧侶や教師などを表してるとされており、そのように普段は落ち着いた人たちでも走り回るほど忙しい月、ということで、12月は「師走(しわす)」と呼ばれるようになりました。
月の異名を語呂合わせで覚える
月の異名の意味や由来がわかったことで、より何月がどんな異名なのかがわかりやすくなります。…が、それでもなかなか一発では覚えられません。
今すぐに覚えたい!という人は、語呂合わせで頑張ってみましょう。
む(睦月)
き(如月)
やすい(弥生)
う(卯月)
さぎ(皐月)
み(水無月)
ふぃー(文月)
は(葉月)
な(長月)
かんで(神無月)
しっ(霜月)
しん(師走)
文章としては意味不明ですが、一度覚えてしまえば簡単です。