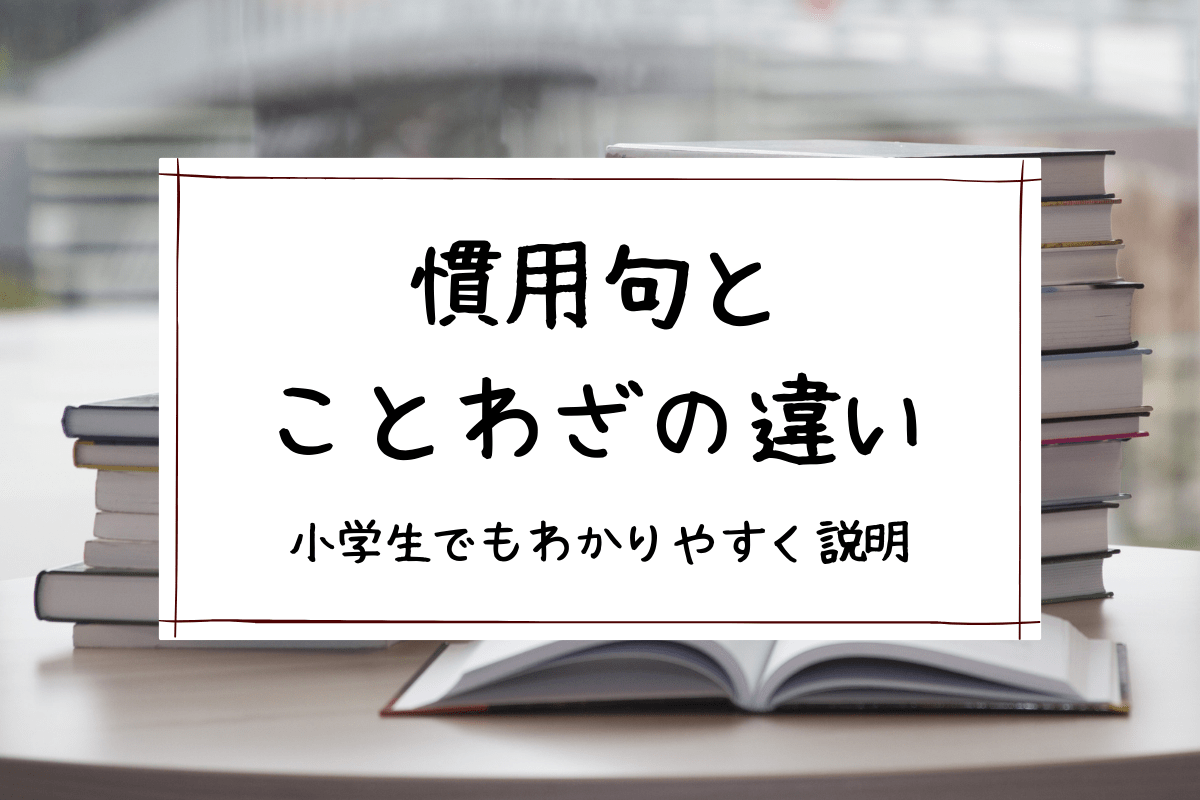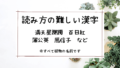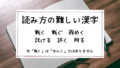昔から使われてきた言い回しで、2つ以上の言葉で新しい意味を持ったもののことを「慣用句」や「ことわざ」と呼びますよね。しかしことわざと慣用句って、いったい何が違うのでしょうか。
スポンサードサーチ
「慣用句」と「ことわざ」はここが違う
まず結論から書くと、慣用句とことわざを分ける際のポイントは、以下の通りです。
★アドバイスなどが含まれている→ことわざ
「慣用句」とは
まず慣用句というのは、昔から習慣として多く使われてきた言い回しのことを言います。基本的には2つ以上の単語をつなげて構成されており、日常の行動について省略した形の言い回しになっているのが特徴です。
例えば、
・耳にたこができる
・腕が鳴る
・大きな顔をする
・顔から火が出る
これらはすべて慣用句ですが、文章に展開してみると、こうなります。
・同じ話を何度も聞くと、手や足にたこができるのと同じように、耳にもたこができそうだ
・自分の腕(技量)を知らしめるために鳴こう(声を上げる、という意味)
・まるで顔が大きく見えるほど、威張った態度をとっている
・顔から火が出ているように真っ赤になるほど恥ずかしい
いちいち「足が疲れすぎて感覚がなくなり、まるで足ではなくただの棒がくっついているように感じるんだ~」なんて、長ったらしくて言うほうも聞くほうも面倒ですよね。省略して「足が棒になったよ」で十分意味は伝わります。こんな風に、身近な言い回しを省略した表現が定着したものが、慣用句なのです。
・慣用句は短い
・意味が省略された言い回し
「ことわざ」とは
一方で、ことわざは昔からの知恵や大切な教えなどを表した短い文章のことを指します。
・海老で鯛を釣る
・猿も木から落ちる
・馬の耳に念仏
・骨折り損のくたびれ儲け
例えばこれらはどれもことわざで、それぞれにこんな意味があります。
・少しの労力で大きな利益を得られることもある
・その道の達人でも時には失敗することがある
・聞く気がない人にいくら意見をしても全く意味がない
・疲れるだけで少しも成果が上がらないこともある
特徴は、文章に教訓や格言が含まれていること。教訓というのは人に何かを教える時に使う言葉で、格言というのは戒めの言葉を短くしたものです。
もっと簡単に言うと、「これは〇〇だからこうしたほうが良いよ(orしないほうが良いよ)」とか、「これは△△だから気を付けないとね」とか、つまりはアドバイスや注意喚起、励ましなどが含まれているというのが慣用句との違いです。
また、慣用句の場合、前後の文脈によっては意味が変わってしまうことがあります。(例えば、アンパンマンは大きな顔をしている、など)。一方で、ことわざは前後の文脈がどうであろうと、その意味が変わることはありません。
・意味にアドバイスなどが含まれている
・どんな使い方をしても意味は変わらない
「慣用句」「ことわざ」と「故事成語」の違い
慣用句やことわざとよく似た言い回しに、「故事成語」というものがあります。じつは故事成語はことわざの仲間。ことわざの中でも特に主に中国の古典に記された出来事がもととなってできたもののことを、故事成語と呼ぶのです。
例えば、「人間万事塞翁が馬」ということわざがありますよね。この言葉は中国の古典「准南子」に記された内容がもとになって作られています。内容を簡単に紹介すると…
この話をもとにして、「人生の幸不幸は予測しがたく、安易に喜んだり落ち込んだりするべきではない」という意味で「人間万事塞翁が馬」ということわざが作られました。
・故事成語は主に中国の古典や昔話から生まれたことわざ