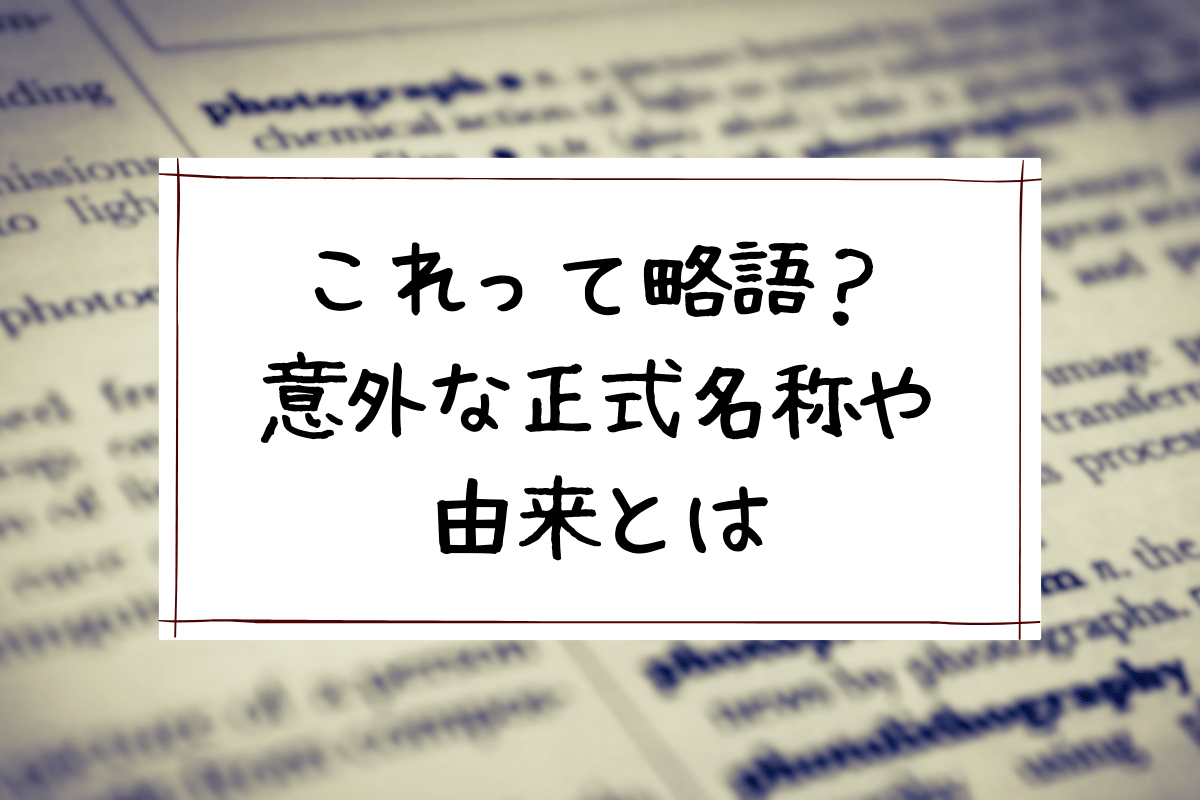普段何気なく使っている言葉が、じつは略語だったってことは良くありますよね。しかし世の中には、皆さんが知らない意外な略語が存在します。
すでに一般化してしまった隠れた略語を、再発見してみましょう。
スポンサードサーチ
重曹
料理や掃除に大活躍の重曹。重曹の正式名称は「炭酸水素ナトリウム」で、別名は「重炭酸ソーダ」。漢字で書くと、「重炭酸曹達」です。
押忍(オス)
押忍(オス、オッス)は、「おはようございます」を最初の”お“と最後の”す“だけに簡略化した挨拶です。現在では朝の挨拶だけに限らず、武道での挨拶や、軽い返事などにも使われていますね。
スポンサードサーチ
ダントツ
ダントツというのは、「断然トップ」の略語です。なので「断突」ではなく「断トツ」。トツはカタカナが正解です。
断トツはそれだけで「トップである」ことを意味しているので、「断トツでトップ」というような言い回しは、正しくありません。
寒天
寒天はところてんを一度凍結させて乾かして作られるため、「寒ざらしところてん」を略して「寒天」と呼ばれるようになりました。
じつは寒天、冬に外に捨てて乾燥したところてんを水で戻して使ってみたら意外とおいしかったという偶然の産物です。
スポンサードサーチ
ピアノ
音楽の授業で習ったことがある人もいると思いますが、本来「ピアノ」という言葉は、音楽用語で「弱い音」を表すものです。楽器としてのピアノの正式名称は、「クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ」。
意味は「ピアノ(弱い音)からフォルテ(強い音)まで出せるチェンバロ」。チェンバロはピアノの元祖である楽器です。なぜ「ピアノ」部分だけが名称として残ったのかは不明。
レーザー
当たり前のように使っているレーザーという言葉ですが、じつは「Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(ライト・アンプリフィケーション・バイ・スティミュレイテッド・エミッション・オブ・ラジエーション)」の頭文字をとったものです。
日本語に訳すと、誘導放出による光増幅放射。
スポンサードサーチ
口コミ
口コミは何かの略語だろうなというのはわかっても、元の言葉が何なのかを知らない人は多いはず。答えは「口頭でのコミュニケーション」を略して口コミです。
マスコミュニケーション、いわゆるマスメディア(テレビ・ラジオ・新聞など)を通じてのコミュニケーションの対比として、生まれた言葉です。
Gメン
「万引きGメン」や「麻薬Gメン」など、考えてみれば「Gメン」って何?って感じですよね。Gメンは「Government Men(政府の役人)」の略語。
元々はアメリカで使われていた隠語であり、政府からの特別捜査官を意味します。ただし日本では、「専門的に取り締まりを行う人」という意味で使われることも多いですね。
「Aメン」や「Bメン」はいません。
割り勘
かかったお金を人数で均等に割って支払いをする割り勘は、「割り前勘定」の略語です。
ちなみに、割り勘というのは日本ならではの概念なんだとか。海外では自分が注文した分を自分で払う、もしくは全額誰かが払って次回は別の誰かの支払いというパターンが多いようですね。
軍手
軍手の正式名称は「軍用手袋」。
今では屋外でのさまざまな作業用として使われていますが、元々は旧日本軍の兵士が使用していたことから、軍用手袋という名前が付けられています。鉄砲を素手で触ると錆びてしまうため、それを防止するために使ったのが始まりです。
カラオケ
何らかの造語であることはわかっていても、じつはカラオケが「空のオーケストラ」の略語だなんて、知らない人も多いのではないでしょうか。
元々は、生演奏のオーケストラに対して「生演奏ではない録音の伴奏=空オケ」だったのです。それが次第に伴奏そのもののことではなく、録音の伴奏で歌を歌うことを、カラオケと呼ぶように変化していきました。
超ド級
規格外を表す言葉「超ド級」ですが、ドは「Dreadnought(ドレッドノート)」という、イギリスの大型戦艦の名前を略したものです。
元々はドレッドノートを超える規模の戦艦を「超ド級戦艦」と呼んでいました。現在では戦艦だけではなく、様々なものや事柄の規模や迫力の大きさを表現する時にも使われていますね。
ちなみに「ド派手」「ド迫力」などの「ド」に関しては、ドレッドノートは関係ありません。これらの「ド」は「並外れた」という意味を持つ接続語で、ドレッドノート誕生よりはるか昔から使われている言葉です。
ボールペン
ボールペンの正式名称は、「ボールポイントペン」です。ポイントは「先端」のことで、先端に小さな球をはめ込まれていることから、この名前が付けられました。
電車
電車の正式名称は「電動機付き客車」もしくは「電動機付き貨車」。蒸気で動く「汽車」の対になる言葉として生まれたわけではありません。