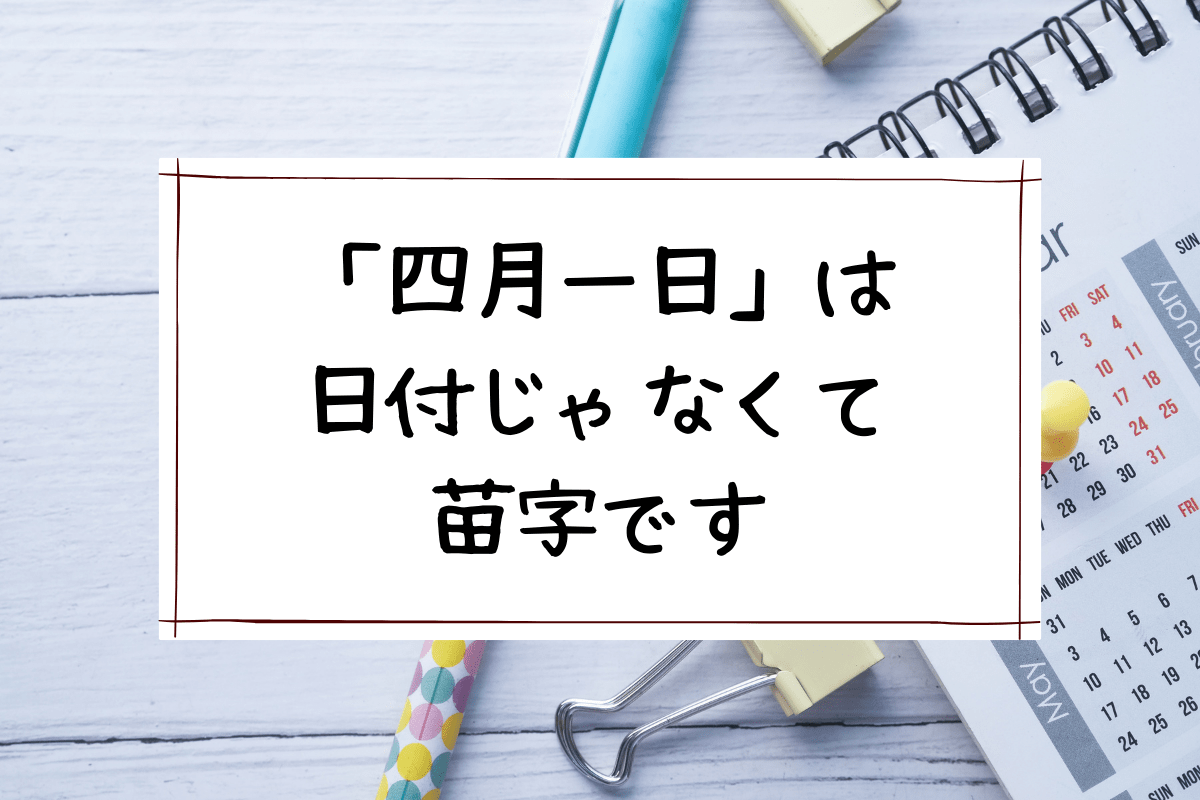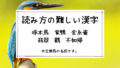日本には約29万種の苗字があると言われています。その中には「佐藤」や「鈴木」など定番中の定番から、日本に数世帯しかないような珍しいものまで。
そんな中でも特に面白いのが、まるで日付のような苗字。「四月一日」これもれっきとした苗字ですが、さてなんと読むかわかりますか?
スポンサードサーチ
なぜ「四月一日」で「わたぬき」?
旧暦の4月1日は、現在の暦で言えば5月の中頃。この季節になると、人々は冬の間に着物に入れていた綿を抜いて薄着になることから、四月一日と書いて「わたぬき」と読むようになりました。
そして四月一日のほかにも、日付が使われた苗字があります。
・四月一日→綿を抜く→わたぬき
・五月七日→梅雨入り→つゆり
・六月一日→瓜が割れる→うりわり
・八月一日→稲穂を摘む→ほづみ
・八月十五日→中秋→あきなか、なかあき
・十一月二十九日→今年ももう少し→つめづめ
・十二月一日→師走→しわすだ
・十二月晦日→新年までもうすぐ→ひづめ、ひなし
・五月七日→梅雨入り→つゆり
・六月一日→瓜が割れる→うりわり
・八月一日→稲穂を摘む→ほづみ
・八月十五日→中秋→あきなか、なかあき
・十一月二十九日→今年ももう少し→つめづめ
・十二月一日→師走→しわすだ
・十二月晦日→新年までもうすぐ→ひづめ、ひなし
この中で、今でも使われているのは四月一日と八月一日くらい。ほかは実在した苗字なのかが定かではないものもあります。
日付じゃないけど面白い苗字
また、おまけに日付以外にも面白い言葉遊びがもとになった苗字もちょっと紹介。
・小鳥遊→天敵のタカがいなくて小鳥が遊ぶ→たかなし
・月見里→山がないと里から月がよく見える→やまなし
・薬袋→殿様の薬袋は中を見ない(殿様の健康状態を探るのはNG)→みない
・月見里→山がないと里から月がよく見える→やまなし
・薬袋→殿様の薬袋は中を見ない(殿様の健康状態を探るのはNG)→みない
日本にある苗字の数
元々「苗字」というのは中国の文化。中国では約3000種類の苗字がありますが、日本は冒頭でも紹介した通り、なんと29万種類もの苗字があると言われています。同じ漢字でも読み方が違うもの(羽生:はぶ・はにゅう、など)などを除いても、15万種類以上。
しかもさらに驚くのは、このうちの約7000種類で、人口の約96%をカバーしているということ。つまり残りたった4%ほどの人口に、28万種類以上の苗字が存在しているということです。
今回紹介した「日付のような苗字」に限らず、珍しい苗字というのは数えきれないほどあるということですね。
そんな珍しい苗字たちについて調べるうちに、1冊の本を発見。
リンク
単にどう読むかや由来だけではなくて、実際にその苗字を持つ本人にインタビューして、苗字にまつわる面白エピソードなどが満載です。もしかしたら、自分の苗字が載っているかも?気になる人は、ぜひ読んでみてください。