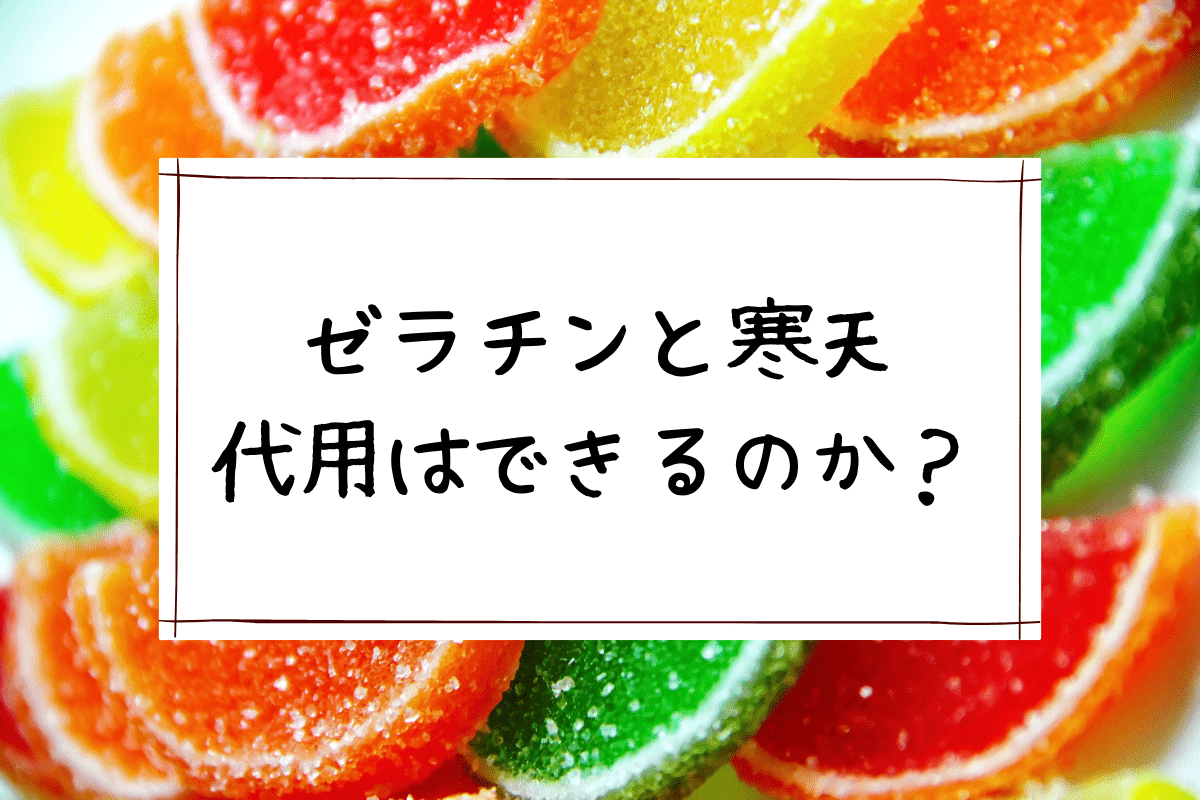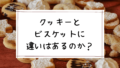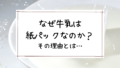ゼラチンと寒天、どちらもゼリーなどによく使われる素材ですが、何か違いはあるのでしょうか。それぞれに代用は可能なのか?という点に焦点を当てつつ、その違いを紹介していきます。
スポンサードサーチ
ゼラチンと寒天の違いと代用時の注意点
ゼラチンと寒天はお互いに代用OKですが、そのまま同じ扱いでOKというわけではありません。注意すべき点は、4つです。
・固める時の温度
・作った後、常温に置く場合
・食感の違い
原料の違い
ゼラチンの原料となるのは、牛骨・牛皮・豚皮・魚などから作られたコラーゲン。コラーゲンに様々な処理を加えたうえで抽出された動物性たんぱく質が、ゼラチンなのです。
一方で、寒天の原料となるのはテングサやオゴノリなどの海藻。テングサやオゴノリには食物繊維で構成された粘液質が含まれており、煮沸→濾過→凝固→凍結を経て、粘液質の食物繊維のみ残ったものが寒天です。
これにより食感にも違いが生まれ、ゼラチンはプルプルとして舌ざわりが滑らか、寒天はしっかりと弾力のある食感となります。
カロリーの違い
ゼラチンのカロリーは、メーカーにもよりますが100gあたり約350kcal。対して、寒天のカロリーはほぼ0kcalです。
ゼラチンのほうが大幅にカロリーが高いと感じてしまいますが、ゼラチンを実際に使う量は少ないため(ゼリー1人前あたり1~2gほど)、さほど気にするようなレベルではありません。
溶ける温度の違い
ここが一番重要なのですが、ゼラチンと寒天では、調理する際の「溶ける温度」が違います。
ゼラチンの溶ける温度は50~60℃なのに対して、寒天は90~100℃。つまりゼラチンを溶かす要領でぬるめのお湯を使ってしまうと、寒天がうまく溶け切らずに、失敗してしまう可能性があるということです。
そして逆に、ゼラチンは溶かす温度が高すぎると、たんぱく質が変質して固まりにくくなってしまうという特徴があります。ゼラチンを溶かすとき、寒天のように熱湯を使ったり、グツグツに詰めたりするのはNGです。
固まる温度の違い
もう一つ重要なのが、ゼラチンと寒天の「固まる温度」の違い。ゼラチンが固まるのは20℃以下ですが、寒天が固まるのは30℃以下です。つまり、寒天は真夏でもなければ常温でも次第に固まってきますが、ゼラチンの場合は冷蔵庫に入れないと固まらない場合が多いです。
再び溶ける温度の違い
さらに、一度調理したゼラチンや寒天が再度溶ける時の温度にも、違いがあります。一度固まったゼラチンが再度溶ける時の温度は25度以上。それに対して、寒天の場合は38℃前後です。つまり寒天で作ったものは常温で溶け出すことはないけれど、ゼラチンで作ったものの場合は、夏場だと常温で溶けてきてしまうということですね。